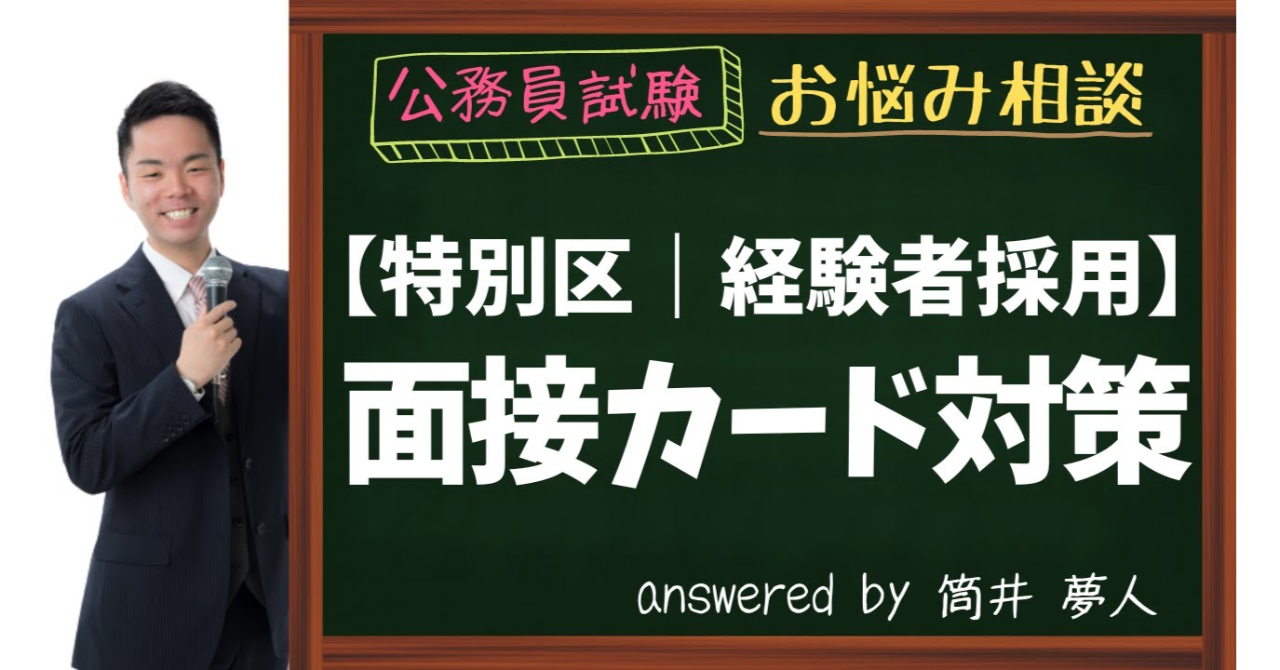今回は特別区経験者採用 面接カード(職務経歴書)のポイントというテーマでお届けします。
皆さん方もいよいよ面接カードの提出期限ですね、少しずつ近づいてまいりましたけれども。このカードについて、どういう感じで書けばいいのかなと悩んでいる方がたくさんいらっしゃると思うんですね。
ですのでそういった皆さん方に向けて、各設問項目ごとにここは最低限意識してくださいということをご案内していきたいと思います。
1級職・2級職の方どちらにとっても参考になる内容だと思いますので、すでに面接カードの内容を仕上げた方もこの記事をお読みいただき、自分自身のカードがネガティブなものになっていないかぜひチェックをしていただきたいと思います。
なお、下記のYouTube動画でも解説を行っているので、併せてご視聴ください。
全てに触れつつ全てを語らない
設問1のポイントが、全てに触れつつ全てを語らないということであります。
全てに触れつつ全てを語らないってどういうこと?と思われるかもしれないんですけども。まずは「全てに触れる」ということの意味をご案内してまいります。
設問1って皆さん方もすでにご存じのことかと思いますけれども、一番要求されているトピックが多いですよね。
志望理由を書かなくちゃいけないでしょ、あとは職務経験も書かなきゃいけないし、携わりたい職務、そして実現したいことについても触れなくちゃいけない。ということで、他の項目と比較したときに明らかに要求されているトピックが多いのが設問1の特徴なんです。
でも要求されているわけだから、それらについて触れないわけにはいかないじゃないですか。これが「全てに触れてほしい」っていうことの意味なんですよ。しっかり要求されているトピックについては、その全てを書いてください触れてください、これがまず1つ目のポイントですよね。
あわせて強調しておきたいのが「全てを語らない」って何ですか?というところなんですけども。
先ほど挙げたトピックについて320字しか皆さん方には文字数制限がないんですよ。例えばこれが1,000字ありますとか2,000字ありますっていうことだったら、もう事細かに大量にそれぞれのトピックごとに書けると思うんですよ。
でも320字しかないということを考えると、全てのトピックについて仔細にわたって説明することってほとんど不可能ですよね。
ということでね、これ、真面目な方ほどこのトレードオフで悩むんですよ。つまり、全部について触れなきゃいけないんだけれども詳細は書けないじゃん…ということで、設問1って悩む方がすごく多いと思うんですけども。
でもそんなときは「全てに触れつつも全てを語らない」これを鉄則として守ってほしいと思いますし、語れなかった部分については面接に入ってから話していくんだ!というマインドが絶対に不可欠であります。
ですから設問1については、各トピックについてフックとなるようなキーワードとかを入れていこうというマインドが一番現実的ではないかなと思います。
通常の業務フロー以外の話に
設問2のポイントが、通常の業務フロー以外の話にするということであります。通常の業務フロー以外の話って何?と感じるかもしれないんですけども。これは要するにこういうことです。
設問2で明らかに力点が置かれているのは「自ら考え行動」の部分ですよね。この部分が他の設問とは明らかに違う。この設問2を最も特殊たらしめている要因だと僕は思っているんですね。
それを考えたときに、例えば皆さん方が日常のありふれた業務フローの話をしたとするじゃないですか。そうなるとたぶん、「あの、これって自ら考えたというか業務フローの一貫としてやっただけですよね?」という風に解釈されるリスクが高まっちゃうということなんですよ。
例えばGravityの過去の受講生で、市役所職員の方だったんですけども。その方がね、一番最初僕らの添削が始まったときに「ダブルチェックをしました」みたいなことを書いたんですよ。これどこの市区町村もそうだと思うんですけども、書類とかを作成するじゃないですか、そこについてダブルチェックをしっかりしましたみたいな。そういった話を書いてたんですよね。
ですけれどもこれ、皆さん方聞いてみてどうですか?公務員がダブルチェックするのなんて当たり前じゃない?って感じませんか?
もちろん組織によっては、ダブルチェックというのはありませんというケースも当然あるとは思うんですよ。なんですけれども面接官からしたときに、「でもダブルチェックって別に通常の業務フローに入ってることもあるよな」という風に主観的に判断されちゃうということなんですよ。
通常の業務フローの話だよなと思われれば思われるほど、これ自ら考えたことじゃないよなと解釈されちゃうということなんですよね。
ですから自ら考えましたと言うためには、通常の業務フローの一環ではない領域の話をしなくてはいけないということがポイントになってまいります。
ですので、面接カード(職務経歴書)の設問2を見返したときに、これどうもこの職種・この業界だと通常の業務フローっぽいかもなと感じた場合には、別のエピソードあるいは別の切り口を用意したほうがいいかもしれません。
「引きの強さ」を意識しよう
設問3のポイントが、「引きの強さ」を意識しようということであります。
まず設問3が最も他の設問と異なっているのは「失敗の許されない状況」について書いてくださいと要求されていることですよね。失敗が許されない状況というのは言い換えれば「絶対に成功させなくてはいけない話」なわけじゃないですか。
となってくると当たり前なんですけれども、面接官としては引きが強いエピソードを書いてくれよって思っているに決まってますよね。
設問の2・3・4というのはどれもエピソードトークを求められる点では共通してるんですけども、ただ最も引きの強さが要求されるのは絶対に設問3であると私は確信しています。ですから、もしも設問3の引きが弱い場合、面接官からの評価は残念ながら高まる方向にはいきません。
例えば過去のGravity受講生の中で、営業マンをやってますという方がいらっしゃったんですね。毎年営業マンをやってますっていう方たくさんいらっしゃるんですけれども。営業マンの方が書きがちなエピソードに「ノルマ」の話を書くんですよね。まぁノルマ、確かに営業マンからすると失敗は許されないんでしょうけども。
ただ重要なのが、そんなの当たり前じゃない?っていう話じゃないですか。営業マンがノルマに追われている、目標に追われている。そんなのって通常のことであって、別に失敗が許されない・絶対に成功させなきゃいけない、そこまで引きの強いエピソードかというと、ただ書いただけではそう感じることってできないですよね。
ですからこういうエピソードを書いた人は、「でもこれって営業マンだと普通のことだと思うんですけど?」って面接官から言われたりしてるんですよ。そうなってしまうと「じゃあ他にありますか?」ということで、結局そこに書いたエピソードじゃない別の強いエピソードを言ってくれよって要求されてるんですよね。ということは、やっぱりこの設問3では引きのある強いエピソードを書かなくちゃいけない。
でね、この面接カード(職務経歴書)については、「一般的なエピソードを書いておけば大丈夫ですよ、面接で追及されることはありませんから」っていう優しい言説が流布されすぎた結果として、皆さん引きの弱いエピソードばっかりになってるんですよね。これはGravityのような予備校に通っている人であっても、一番最初に提出される内容は引きがどうも強くないなっていうものになってしまってる。
例えば我々が添削をしていった例でいうと、その方はね警察官の方だったんです。その方が一番最初に書いていたエピソードっていうのは「周囲のパトロール」のことだったんですよ。巡回というんですか、そういう話を書いてたんですよね。分かるんですよ、確かにパトロールとか地域の巡回とかね、失敗は許されませんよ。
だけど違うなって皆さん方も感じるでしょ?どうしてかって言ったら、警察官が地域のパトロールをするなんて日常のことじゃないですか。絶対に何が何でも成功させなくちゃいけないというものとはちょっとだけ違う感じがしますよね。
その方にね、もう私は問答無用で「これはダメです!違うエピソードにしましょう」ということを提案しました。で、他に例えばちょっと特殊だったなっていうエピソードってありませんか?みたいなことを伺ってたんですよ。
そしたらですね、「そうですねパトロール以外だと…G7の警護に関わったことがあります」って言ってきたんですよ。
そういうのを持ってこい!それでいきましょう!と。
で、G7の警護なんてすごい話じゃないですか。先進国首脳たちの会議を警護する役割でしょ。この話って、警察云々についてあまり詳しくない我々素人とか面接官から見たときに、”G7″っていう話だけでスゴ味が伝わるじゃないですか。
ということで、この設問3で求められているのはとにかく引きの強さです。それ以外のこと、あまり細かいことを考える必要はございません。もちろん人によっては、そんなすごいエピソードいくつもないよ…とか、あんまりないな…っていう方もいると思うんですけども。
でも自分のエピソードを色々洗い出していったときに、相対的にはたぶんこれが一番引きが強いだろうなっていうのはあると思うんですよ。そのエピソードについては、最も引きの強さが求められている設問3にしっかりブチ込んでくださいということであります。
【1級職】それは「チーム」なのか?
最後に設問4についてご案内したいと思います。設問4については1級職なのか2級職なのかによって書く内容が異なってまいりますので、1級・2級をそれぞれ分けた上でご案内していきたいと思います。
まず1級職については、それはチームの話なのか?ということであります。
この設問4番、1級職の方の場合には特に明文化された形でチームとしての話を書かなくちゃいけないわけですよね。では、チームって何ですか?ということを少し考えてみましょう。ここでは辞書の定義から少し引用したいと思うんですけれども。
チームとは
①団体競技で勝敗を争う、それぞれの組。
②共同作業を行う、数人から成る集団。新明解国語辞典(第八版) 三省堂
ここで重要なのが、②に書いてある「共同作業」という項目であります。要するに、自分単独じゃなくて周囲の人たちと一緒になって共同で何かをやります。そのときに我々は「チーム」という表現を用いるわけですよね。
どうしてここまで”共同”という要素を強調するのかというと、多くの受験生の設問4の内容を読んでいると、「これ共同作業じゃなくて単独の作業の話になってますよね?」という方がすっごく多いんですよ。
自分がどういう役割でどういう行動をしたのかっていうのは確かに書かれてるっぽく見えるんだけど、どう読んでもこれチームプレーの一環としてこういうことをやったというよりは、ただ日常の単独作業を書いてるだけだよねって感じられるものがすごく多いんですよね。
でもそういう形で、これ単独作業じゃない?と解釈されてしまうと、面接官から「これチームとしてやったことなんですか?」と追及されてしまいかねないわけですよ。
もちろん最終的にはチームプレーであろうが、自分自身が行う作業自体は単独作業ではあるじゃないですか。それは私もよく分かっています。
ですけれども重要なのは、皆さんの行った単独作業っていうのが、ちゃんとチームの共同作業の一環としてこれは行ったんですよっていうレトリックになっているのか。すなわち設問4がちゃんとチーム味を演出できているのかどうか、というところを注意してほしいということであります。
【2級職】そこに「一般性」はあるか?
次に2級職ですが、そこに「一般性」はあるか?ということであります。この設問4番、2級職の方の場合には、後輩とか部下の指導とか育成で最も意識したことを書かなくてはいけないわけですよね。
このときによくよくあるのが、自分が後輩とか部下を指導した具体的なエピソードだけに話が留まっているケースなんですよ。具体的に説明しましょう。
過去Gravityの受講生でスポーツジム勤務の受講生がいたんです。その方は店舗を任されていて後輩とか部下もいるわけですよね。指導しなくちゃいけません、と。
そのときに一番最初に記載されていたのが、スポーツジムの様々な器具あるじゃないですか、色々筋トレ用のね。そういった様々な器具について、どうやって使っていくのかを教えた、みたいな。あるいはお客様が来店されたときに、どういう風に接客するのかを具体的に実演してみせた、とか。そういったことだけがつらつら書いてあったんですよ。
でね、これもしかしたら皆さん方からすると、何が悪いのかな?って感じるかもしれない。でもこれは明確にダメな例です。どうしてか?理由は明快で、だってその経験って特別区で直接活かせないじゃないですか。
これ言うまでもないんですけれども当たり前ですよね。だって特別区はスポーツジム運営してないじゃないですか。だからスポーツジムにある器具の使い方を誰かに教えるシチュエーションなんてないわけですよ。
店舗にいらしたお客さんにしたって、スポーツジムに来店した方に過ぎないわけでしょ。実際特別区がスポーツジムを運営してない以上は、そこだけの話になってしまうと特別区で別にそれって活きないですよねという話に終わっちゃうじゃないですか。
つまりこういうことですよ。具体的なエピソードだけの列挙になっていると、その経験の適用範囲がものすごく限定されてしまうということなんです。ですからこの場合は、書かれた具体っていうものをもうちょっと抽象化して一般性のあるものにしないといけない。
先ほどの教えに一般性を付与するのであれば要するにこういうことでしょ。「部下や後輩に指導をする際には、まずは自分が実演して説明をすることを意識しました」こういうことじゃないですか。すなわち実際に自分が後輩の前で、これこれこういう風にやるというのをやってみせる、と。これが先ほどの具体的なエピソードを一般化した形ですよね。
こういう形で一般性を持たせたのであれば、特別区に入ってから部下や後輩の指導・育成をすることはあるわけですから、そのときに、「あっなるほどこの人は実際に自分がやってみせるという形でまず指導をしていくんだな」ということで、面接官にも具体的な皆さん方の経験とかノウハウが活きる絵を説明しやすくなりますよね。
ですのでぜひ2級職の皆さん方にあっては、この設問4について単に具体を列挙するだけになっていないか、しっかりと一般性を持たせているかチェックしてほしいと思います。
ということで今回は、面接カード(職務経歴書)の各設問項目において重要となるポイントをご案内しました。ぜひ提出する前のタイミングで改めてこちらの記事を確認した上で、今日のポイントをしっかり踏まえたものになっているか再度チェックをしていただきたいと思います。
✅2000名以上が登録中の公式LINE!

特別区経験者採用を受験するなら登録必須のGravity公式LINE!
受験生のほとんど(2000名以上)が登録中で、既に有料級情報を手に入れてます!
✅LINE限定情報の配信
✅本試験講評動画の視聴
✅イベント(定員制)の優先案内
✅時事対策に役立つ最新情報を提供
ご登録は下記URLから!